第2回 研究会報告 【マウリツィオ・カーゲル】

*第2回現代音楽舞台研究会
日時:2014年5月31日(土)13:00-16:30
場所:愛知県立芸術大学博士棟演習室
テーマ:マウリツィオ・カーゲル《Match-für drei Spieler》
(邦訳:3人の奏者のための“試合”)
司会:高山
書記:牛島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【研究会の進行】
(1)《Match-für drei Spieler》の音響的要素のみ(視覚的要素を排除した状態)の聴取
(2)同作品の演奏映像(音響的要素に視覚的要素を伴った状態)の視聴
(3)カーゲル監督による映画 《Match-für drei Spieler》の視聴
(4)(参考作品として)《l'art brut》の紹介及び文楽作品との関連について
〈資料〉
・楽譜:マウリツィオ・カーゲル《Match-für drei Spieler》、《l'art brut》
・インタビュー記事「マウリツィオ・カーゲルが語る“音の演劇”」
(『音楽芸術』1994年1月号pp.60-63)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【当日の様子】
研究会顧問の久留智之先生、ドイツ演劇がご専門の大塚直先生に加え、
若い作曲家の方々、作曲専攻で学ばれている学生さん、
ポピュラーミュージックで活躍されているミュージシャンの方や
磁器作家さん・・・等々、
多彩な分野の方々がご参加下さり、活発な意見交換が行われました。

《2つの異なる方法によるMatchの鑑賞》
Matchの楽譜には、カーゲルによって詳細に演劇的動作の指示が書き込まれているにも関わらず、カーゲル自身はこの作品の鑑賞を「音響的要素のみの状態」と「視覚的要素を伴った状態」の両面から求めています。このことに従って、今回の研究会ではMatchを上記2面から鑑賞しました。
【方法:最初に、用意したMatchの映像から音だけを抜き出し聴取。その後、元の映像を視聴。】
(1)音響的要素のみの聴取
★聴取を終えて
・音のみでも作品として成立している。
・台詞を喋っているかのような音の身振りを感じる。
・トムとジェリーのように、音によって人物の動きが表現されているかのよう。
・この作品は元々、ヘーアシュピール(ドイツのラジオドラマ)で放送することを想定して発想されたという話がある。音によって情景を思い浮かばせる意図があるのでは。
★複数の種類の音響的要素の把握について
・同じ音響的要素でありながら、「台詞(言葉を伴う音響)」は明らかに
「楽器による音響」から浮かび上がって聴こえる。声の力、或いは言葉の力。
(2)視覚的要素を伴ったものの視聴
★視聴を終えて
・視覚的要素によって、抽象的であった「音」に意味の方向性が生まれる。
(→単にカラカラ・・・と聴こえた音は、サイコロを振る音であったと分かった。
それによって、サイコロによってその後の進行を決めるという、
一般的な音楽ではあり得ない適当さ、滑稽さ、賭け事、ゲーム的な印象を
音に付加して観客に与えている。)
・楽器が持つ文化的意味(カスタネット=フラメンコ)も、重要な暗喩となっている。
・奏者は随分感情的に演奏しているようだが、カーゲル自身の指示はどこまで?
(→Matchの楽譜には“感情”に特化した指示は一箇所だけ。との回答あり)
・演奏行為から自然に演劇的動作が生み出されている。
★カーゲル作品の魅力、或いは作家性について
・カーゲルの作品には特有の皮肉・風刺があると同時に、
良く練られた漫才のように仕掛けに満ちている。
・一度の視聴では捉えきれないことが多いが謎が更なる興味を引く。謎が謎を呼ぶ魅力。
・カーゲルという人物そのもののキャラクターに、
すでに作品視聴の前提が含まれているのではないか。
《映画Matchの視聴》
音のみと映像の2面からの鑑賞を経て、様々な意見交換がなされる中で、
演奏家という解釈者を挟んでの実演は、必ずしもカーゲルの意図に沿うものであるとは限らない、との意見も上がりました。(一般的な、楽譜を介する形で行われる演奏が全てそうであるように)そのような意味では、カーゲルが自ら監督したMatchの演奏映画には、カーゲル自身の本来の狙いが、少なくとも1つの方向からは実現されていると言えます。そのような前提を持って、映画の視聴を行いました。
★視聴を終えて
・これが彼の一番やりたかった表現であると感じる。
・カーゲルの人間らしさ、個人的な苦悩を感じる。自分を滑稽に捉えているのでは。
★奏者の頭に鳩が乗っているシーンについて(映像表現におけるナンセンス)
・鳩である意味はどこにあるのか。
・カーゲルは暗喩に満ちた人である。その意味では確実に意図があるのでは。
・言葉では表すことのできない意味の重要性
★その他
・カーゲルの他の作品には、「過去10年(?)クラシックの舞台上で使われていない
楽器を使うこと」等の指示があるものがある。
・彼には、現代音楽の歴史を背負っているという意識がある。
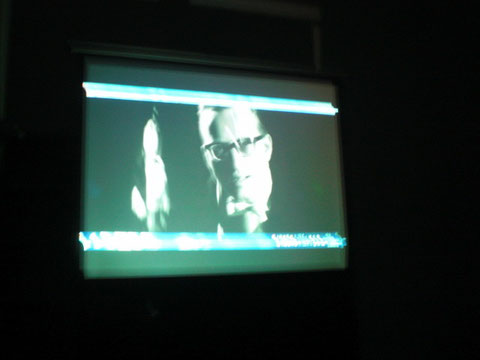
《l'art brutの映像の視聴》
最後に、ドイツ在住の打楽器奏者である渡辺理恵さんから、
文楽に影響を受けているという話があると教えて頂いたカーゲル作品、
l'art brutを鑑賞、意見交換を行いました。
丁寧にしたためられた渡辺さんのメールからも、多くの示唆を頂きました。
【渡辺さん、本当にありがとうございました!】
★文楽との関連について
・元々、西洋に“黒子”という考え方はあったのだろうか?
・西洋の舞台は全てがリアルであり、東洋とはまるっきり約束事が違う。
・舞台というのは、舞台上の進行と、それを観る観客との間にある暗黙の約束事が、
鑑賞のための前提となるものであり、カーゲルが文楽に影響を受けたとすれば、
そのような部分においてではないか。
・黒子によって進行させられてゆきながら、主は打楽器奏者である。暗黙の主従関係があるのでは。
(文責:高山、牛島)

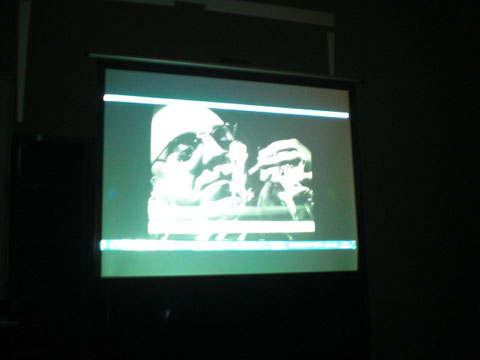
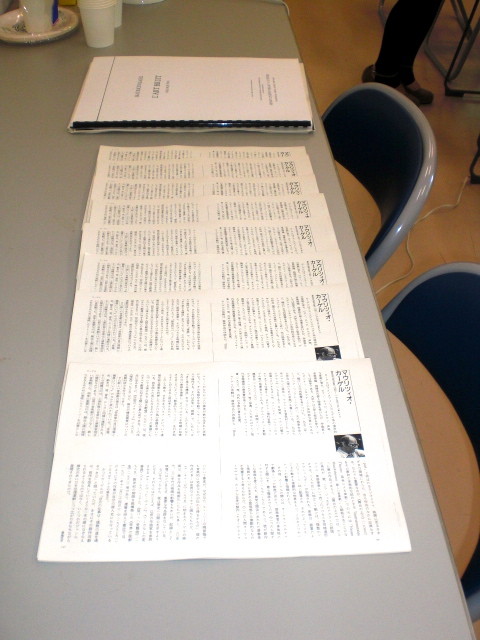
 現代音楽舞台研究会
Association of Contemporary Music Theater
現代音楽舞台研究会
Association of Contemporary Music Theater